食品関連事業者のための製品の減塩ガイドを公開 事業者の自主的な減塩の取組を支援する実践的手引き
研究成果のポイント
- 食品関連事業者による自主的な減塩の取組(製品改良等)を支援する実践的ガイドの作成
- 減塩目標の設定や体制づくりに関する基本的な考え方の整理
- 今後の減塩推進に向けた基盤整備
概要
食品関連事業者(以下、事業者)による自主的な減塩の取組は進められてきましたが、実際に製品改良を進めるための具体的な方法や、それを支援する資料は十分ではありませんでした。
今回、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(大阪府茨木市、理事長:中村祐輔)国立健康・栄養研究所栄養疫学・政策研究センター栄養社会科学研究室の池田奈由室長らの研究グループは、事業者が自社の状況に応じて減塩目標を設定し、製品改良を計画・実施する際に活用できる「食品関連事業者のための製品の減塩ガイド」を作成しました。
本成果は、事業者の自主的な減塩の取組を支援し、今後の減塩推進に向けた実践的基盤の整備につながるものです。
本研究は、厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業)の支援を受けて実施されました。
研究の背景
日本人の1日あたりの平均食塩摂取量は約10gで、経年的に減少傾向にあるものの近年は横ばい傾向が続いています。また、日本人の1日あたりの平均食塩摂取量は、世界保健機関(World Health Organization:WHO)が推奨する食塩摂取量1日あたり5gを大きく上回っており、日本は世界的にも食塩摂取量の多い国の一つに位置づけられています。
こうした状況を踏まえ、厚生労働省が推進する「健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブ」では、食塩の過剰摂取を優先的な栄養課題の一つと位置付け、産学官等の連携によって減塩を実現するための取組が進められています。同イニシアチブにおいて、事業者による自主的な減塩目標設定が進められていますが、実際に減塩の製品改良を開始する、又は既存の取組を見直そうとする事業者、特に中小企業にとっては、具体的な事業計画を立てるために必要な情報や参考事例が十分でない状況がありました。そこで本研究グループでは、国内の事業者が自主的に減塩に取り組む際に活用できる実践的な参考資料として本ガイドを作成しました。
本研究の内容
本ガイドは、本編3章と資料編で構成されています。
第1章では、事業者による自主的な減塩の取組の重要性について、国民の栄養改善とビジネスの両側面から示しました。
第2章では、事業者の減塩目標設定の参考となるよう、対象製品、ナトリウム(食塩)含有量の目標値、実施期間の設定の考え方をまとめました。ナトリウム含有量の目標値については、具体的な方法として売上加重平均ナトリウム含有量と日本版栄養プロファイリングモデル※の活用方法を示しました。
第3章では、減塩の取組を進めるための組織体制の参考となるよう、事業者内部の体制構築及び外部機関との連携について整理しました。外部機関との連携には、行政や事業者間の協働を促進する政府主導の「健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブ」をはじめ、学術関連機関が事業者を支援する2つの取組を例示しています。
資料編では、事業者による減塩目標設定の事例として、海外5社と国内3社の取組を紹介しました。
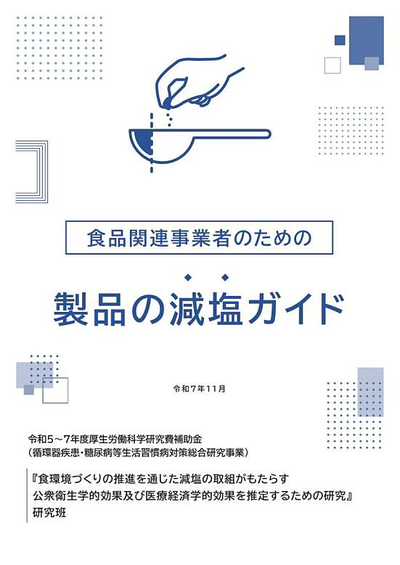
本研究成果の意義
本ガイドは、国内外の減塩政策や事業者の取組状況を踏まえて作成されたものであり、日本の事業者が自主的な減塩を進める際の実践的な指針を提供するものです。特に、減塩の製品改良に着手したばかりの事業者が、自社の状況に応じて具体的な事業計画を立案するための枠組みとして活用できる点に意義があります。
一方で、実用性のさらなる向上に向けて、減塩目標の設定に活用できる指標の整備や、事業者による製品改良の実例の蓄積が今後の課題として挙げられます。引き続き、事業者や関係機関との連携を通じてガイドの内容を発展させ、より実践的で効果的な減塩推進の支援につなげていくことが期待されます。
特記事項
本研究成果は、2025年11月5日(日本時間)に研究班ウェブサイトにオンライン掲載されました。
本研究は、2023~2025年度厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業)「食環境づくりの推進を通じた減塩の取組がもたらす公衆衛生学的効果及び医療経済学的効果を推定するための研究」(課題番号:23FA1012、研究代表者:池田奈由)の支援を受けて行われました。
日本版栄養プロファイリングモデル
栄養プロファイリングモデルは、疾病予防や健康増進を目的として、食品・飲料の栄養成分を総合的に評価する科学的手法です。健康的な食品の開発・流通・利用を促進するため、諸外国では食品の栄養価に応じて食品をランク付けする際に、栄養プロファイリングモデルが活用されています。日本では2024年に日本版栄養プロファイリングモデルの初版が開発され、市販される加工食品や料理に適用可能な加工食品版及び料理版が提案されました。
本件に関するお問合せ先
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

トップページ「新着情報」欄に表示する画像
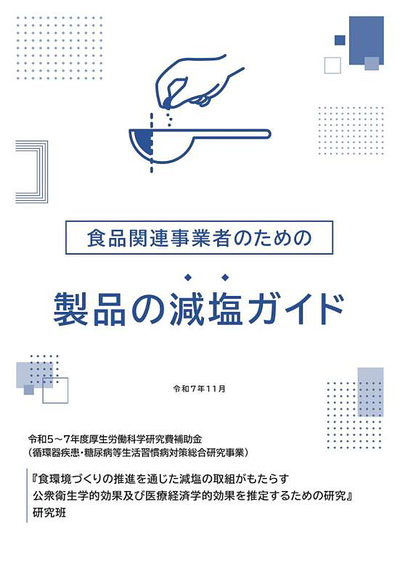
研究成果 / イベント / 公募 / お知らせ のいずれかを入力してください。
研究成果
